どうも、海馬(@Transtier)です。
今日はとても感情を揺さぶられることがありました。”感情を揺さぶられる”とポジティブに捉えられそうに書いてみましたが、実際は非常にネガティブなことです。
久しぶりに頭に血が上る感じがして、職場から帰る頃には足の血液が全て上半身に集まっていたような気がします。おかげで、足元がふらつくこと。。。
そんな時、ふと姿勢に意識を向けると、誰がどう見ても落ち込んでいる人になっていました。肩は耳より前に出て、背中は丸くなり、首は前に突き出ている。教科書通りの猫背で、見ている人にも陰鬱な印象を与えかねない姿勢です。
これではいけないと思い、感情と動作について、改めて学んでみることにしました。
目次
感情と動作の関係
感情と動作のつながりについて
感情と動作。日本語ではそれほど関わりがあるように思えない2つの言葉ですが、英語に直してみるとちょっと違って見えます。つまり、
- 感情:emotion
- 動作:motion
ですね。
感情である”emotion”の中には、動作という意味の”motion”が含まれています。つまり、感情に深く関わっているものが動作だと考えられるかもしれません。
例えば仕事に疲れて気分が沈んでいる時はどんな姿勢でいるでしょうか。猫背になり、溜息をつきながら行動が遅くなり、顔の筋肉も緩んでしまっている。そんな人が多いですよね。
逆に、気分がいい時はどんな姿勢になっているでしょうか。胸を張って表情に活気が宿り、キビキビと行動しているような気がします。
動作を変えるから感情が変わる
動作や姿勢というのは、先に感情があり、その結果として体で表現するものだと考えていました。しかし、最近ではそれは違っていると考えられていますよね。
本当のところは行動によって感情が変わっているというのが正しいようです。楽しいから笑うのか、笑うから楽しいのかということがありますが、これによると笑うから楽しくなるということです。
実際、よく笑う人の近くには人が集まります。それは周りの人たちの感情も変えてしまうからだと思います。感情を変えるためには行動を変えるということを意識して行うことで、嫌な気持ちを簡単に切り替えられるようになるかもしれませんね。
行動からメンタルにアプローチ
ここで終わってしまっては、当ブログのコンセプトである”学ぶ”という部分があまり発揮されていないので、ちょっと異なった角度から書いていきたいと思います。
産能大学通信の専門科目の中で学習をした「しなやかな心をつくるメンタルマネジメント」という科目があるのですが、そちらの中で今回の感情と動作に関連する部分がありましたので、紹介したいと思います。
「動作」から感情に良い影響を与えるコツ
①感情に良い生活習慣を取り入れる
感情に良い効果を影響を与える行動を生活習慣に取り入れるということがまず挙げられます。この科目の中では、アスリートの行動が例として書かれていました。テニスプレイヤーの杉山愛さんです。
杉山愛さんは、メンタルトレーニングの一環で、朝晩30分の呼吸法を実践していました。毎日その呼吸法を繰り返すことで、瞑想の中で、自分が躍動感のある動きで綺麗にボールを捕らえ、打って決める瞬間の心地よいフィーリングまで体感できるようになったのです。
呼吸法というと、あまり動作というイメージはありませんが、やはり意識的に呼吸筋を動かすという点においては動作と言えるのかもしれません。杉山愛さんは呼吸法を日常生活に取り入れることで、常に感情の安定を図っていたんですね。
僕たちアスリートじゃない人たちが取り入れたら良い生活習慣の例として、毎朝出勤前に鏡の中の自分に向かって笑顔で挨拶をするというものがありました。この笑顔を作って自分を肯定することで、プラス思考の回路を作るのに効果的だそうですよ。
②感情を高めるスイッチ(動作)を確立する
これはいわゆるルーティンのことですよね。イチロー選手が打席に入る前の一連の動作が一番有名でしょうか。もしくは五郎丸選手の忍者ポーズもありましたね。
これが一番、今回の記事に関連性が高いような気がします。
緊張しているときや、ミスをしたときは、体まで硬くなり、動きが鈍くなりがちです。そういうときほど、あえて胸を張り、大きな声で話したりするなど、力強い動作を取ってみると、スイッチが切り替わり、攻めの心理状態がつくられるのです。
攻めの心理状態というのがいいですね。気分が落ちている時は、逆に思い切って胸を張って堂々たる姿勢を誇示することにより、気分が乗ってくるということなので、素直に取り入れたい習慣です。
③フィジカルを鍛えることでメンタルを安定させる
健全なる精神は健全なる肉体に宿る
”A sound mind in a sound body”
この部分の説明は、おそらくこの言葉に集約されます。最近だと筋トレがとても重要だということも言われていますし、やはり体がしっかりとしていると、心もしっかりしてくるんでしょうね。このパートでは、元広島の大エースだった佐々岡投手の例が挙げられていました。
佐々岡さんは、体を鍛え上げ、技を磨くことで揺るがぬ自信をつくってきました。キャンプで体を10キロ近く絞り込み、仕上げに300球投げ、全てやりきったという達成感が、「今年1年戦える」という自信になったのです。
ということでした。これは試験勉強でもそうかもしれません。試験会場についたら、後はもう孤独な戦いです。そんな時、ボロボロになったテキストを開いたり、何度も復習したノートを見ることによって、「これだけ勉強してきたんだからもう大丈夫」という自信が湧いてくるものです。
まとめ
というわけで、感情と動作について記事にしてきました。当初は僕が落ち込んだという内容から始まったのに、最終的にはメンタルマネジメントについての話になってしまいましたね。
しかし、今回学べたことは今後の人生においてはとても有意義なものだと思います。
感情が落ち込んだ結果、落ち込んだような姿勢(動作)になるわけではなく、姿勢(動作)を変えるから感情が変わるということです。
もし職場やプライベートで落ち込むようなことがあり、すぐに感情を切り替える必要があると頭でわかっているなら、その時は思いっきり胸を張り、両手を突き上げ、ガッツポーズをしてみましょう。そうすることで自分の感情をコントロールできるようになるかもしれませんよ。
それでは、また。















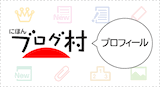
コメントを残す